
庭木の剪定は業者に頼むべき?費用相場・依頼先の種類・自分でできる範囲を解説
2025/11/25
当サイトにはプロモーションが含まれています

2025/11/25
庭木が伸びすぎて「自分で切れるのか」「どこから業者に頼むべきなのか」判断に迷う方も多いのではないでしょうか。剪定は見た目の問題だけでなく、安全性や費用にも影響します。
庭木の手入れは、見た目の美しさだけでなく、安全や住環境にも大きく関わります。ただし、高木や電線付近の作業は思わぬ事故の危険が伴うことから、業者に依頼したほうが安心なケースもあるため、DIYの範囲は慎重に判断することが大切です。
この記事では、業者に依頼すべきケースの基準、費用相場、自分でできる範囲をわかりやすく解説します。

目次

庭木を適切に剪定することで、さまざまなメリットがあります。
庭木の剪定には、樹木が健康に育つこと、見た目を整えることなどさまざまな目的があります。枝葉の伸びすぎといった近隣への迷惑を防ぐ上でも、庭木の剪定は欠かせません。
特に枝が隣家へ越境している場合、民法上は所有者が剪定義務を負うケースもあり、放置すると近隣トラブルの原因になります。
剪定を怠ると、害虫の繁殖や枝折れによる事故、隣家への枝の越境など、思わぬトラブルが発生します。さらに、木が生い茂ると日差しが遮られ、庭の植物の成長にも悪影響を及ぼします。
見た目の美しさだけでなく、家全体の安全と快適さを保つためにも、定期的な剪定は欠かせません。

庭木の種類や高さによって費用は異なりますが、以下が一般的な目安です。
| 立ち木 | 高さ3m未満 | 高さ3〜5m未満 | 高さ5〜8m未満 |
| 5,000円前後 | 5,000円〜1万円 | 1万円〜2.5万円 | |
| 生垣(幅1m) | 高さ1m未満 | 高さ1〜2m未満 | 高さ2〜3m未満 |
| 3,000円前後 | 3,000〜8,000円 | 8,000〜1.5万円 |
※上記の金額は剪定作業のみの目安です。業者によっては「枝葉の処分費」「出張費」「車両費」が別料金となるため、見積もり時に内訳を必ず確認してください。
庭木の剪定費用は、木の高さや本数、剪定後のゴミ処理費用が含まれているかによっても料金は変わります。
また、狭い庭では作業スペースが十分に確保できず作業が難航することから、費用が高額になるケースもあります。

剪定費用は工夫次第で節約できます。
たとえば、複数本をまとめて依頼することで、1本あたりの単価が下がります。また、業者が混み合う春や秋を避け、シーズンオフ(12〜2月)に依頼することも、有効な方法です。
さらに、見積もり時にはゴミ処分費・出張費が込みかどうかを確認しておくと安心です。
同じ作業内容でも業者によって料金差が出るため、条件を比較して選ぶようにしてください。
剪定と同時に、草刈りや伐採、除草などの作業をまとめて依頼できる業者もあります。
まとめて依頼すれば、作業時間や出張費を削減できるため、コストを抑えながら庭全体をきれいに整えることが可能です。

庭木の剪定は、小さな木であれば、自分で剪定することも可能です。たとえば2m以下の低木や生垣、花木などであれば、DIYの範囲で整えることができます。
剪定には、剪定バサミ・高枝切りバサミ・脚立などの道具が必要ですが、無理に高所で作業するのは避けるようにしてください。
一般的には2m前後までがDIYの安全範囲ですが、地面が不安定な場所や傾斜地ではさらに低い位置でも危険が伴います。3mを超える木・電線付近・太い枝の剪定は、転倒や事故リスクが高いためプロへの依頼が推奨されます。
また、3mを超える高木や電線付近の木は、転倒や感電などのリスクがあるためプロに依頼するのが安全です。


剪定を依頼する場合、業者の種類によって費用やサービス内容が異なります。以下の表を参考に、自分に合った依頼先を選んでください。
| 依頼先 | 特徴 | 費用相場 | メリット | デメリット |
| 専門業者 | 樹種や仕立て方に詳しい職人が対応 | 高め | 仕上がりが美しい | 費用がかかる |
| ホームセンター | 手軽で全国展開 | 中〜高 | 店頭で相談できる | 技術差が大きい |
| シルバー人材センター | 地域最安値 | 安い | 地元で安心 | 高木・大木は非対応 |
| ハウスクリーニング業者 | 庭掃除・草刈りもまとめて依頼可 | 中程度 | ワンストップ対応 | 剪定専門ではない |
※業者選びの際は「賠償責任保険の加入有無」も必ず確認してください。枝の落下による破損事故が起きた場合の補償に関わります。
専門業者は費用は高めですが、樹木ごとの特性を理解しており、仕上がりがていねいです。一方で、コスパを重視するならシルバー人材センターやホームセンター提携業者も選択肢になります。


剪定は木の種類ごとに最適な時期があります。季節を誤ると木に負担をかけるため、種類別に適したタイミングを把握しておきましょう。
常緑樹は生育が落ち着く春と秋、落葉樹は葉を落とした冬が最適です。
※落葉樹は休眠期(11〜2月)なら強剪定が可能ですが、常緑樹は強剪定に弱い種類もあるため、切り戻し量は専門業者に確認するのが安心です。
夏は樹液の流れが活発で剪定のダメージが大きく作業工数が増えるほか、業者の繁忙期にもあたるため費用も上がりやすくなります。

剪定業者を選ぶときは、費用の安さだけでなく、信頼性・対応の丁寧さ・安全性をしっかり確認することが大切です。
ここでは、依頼前にチェックしておきたいポイントを紹介します。
剪定業者の信頼度を見極めるには、実績と口コミの確認が欠かせません。
公式サイトに掲載されている施工事例や写真を見ることで、作業のていねいや仕上がりのレベルがわかります。さらにGoogleマップやSNSで実際の利用者の声をチェックすれば、対応の良し悪しも判断しやすくなります。
剪定作業中に枝が落下してガラスを割ったり、隣家の塀を傷つけたりする事故は珍しくありません。
万が一のトラブルに備えて、損害保険や工事保証があるかどうかを必ず確認しておくと安心です。
今後も長く庭の管理を任せる可能性を考えると、信頼して相談できる対応力のある業者が剪定業者が理想です。
見積もり依頼や問い合わせへの対応スピードも、優良な業者かどうか判断する重要なポイントです。対応力に優れている業者は、作業当日もトラブルが生じた際も、誠実に対応してくれます。
「安いから」という理由だけで剪定業者を選ぶと、思わぬ追加費用が発生することがあります。
見積もりを比較する際は、費用とサービスのバランスを重視し、トータルコストで判断することが大切です。
剪定業者を選ぶ際は、これらを事前に確認しておくことで作業後のトラブルを防ぎやすくなります。
特に高木剪定のような危険を伴う作業では、安全管理と保証対応のしっかりした業者を選ぶことが欠かせません。安心して依頼できる業者を見つけるためにも、チェックリストの内容はしっかり把握しておくと良いでしょう。
庭木の剪定は、見た目の美しさだけでなく、安全性や家のメンテナンスにも関わる大切な作業です。
ただし3mを超える高木や脚立を使う作業はDIYでは危険が伴うため、プロへの依頼をおすすめします。また、費用を抑えたい場合は、複数社の見積もりを比較しシーズンオフを狙うのが賢明です。
信頼できる業者に依頼し、安全で快適な庭づくりを実現してください。

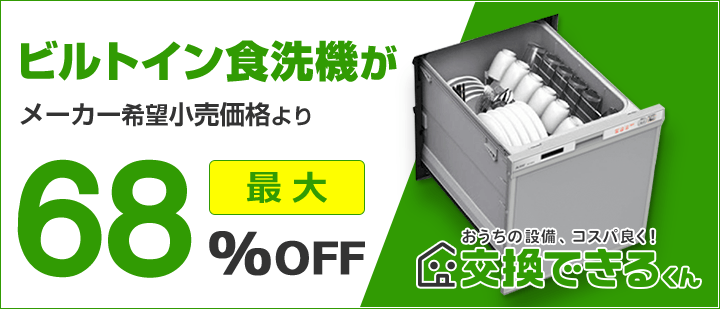

ARTICLE LIST

2023/10/05


2024/04/01